本対談では、フォーカスシステムズの森 啓一 代表取締役社長とFRONTEO守本 正宏 代表取締役社長に、経営者としての信念や事業を通して実現したい社会の在り方、AIソリューションの可能性と期待、今後の展望をテーマに意見交換いただきました。
―― フォーカスシステムズの経営理念、企業として目指していることについてお聞かせください。
森:私は元々財務経理分野の出身で、ITは専門ではありません。そこで、トップである自分は、技術力、知識力といったITそのものより、むしろチームや社員を取りまとめる上で欠かせない「心」の問題を中心にリーダーシップを発揮すべきだと考えました。社長として経営理念、企業としての在り方を整理し、会社の向かっていくべき方向を定めました。「社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のより良い環境作りに貢献する」の経営理念の他に、コーポレートスローガン「テクノロジーに、ハートを込めて。」は社員の間でも好評です。

私自身のITとの関わりは、前職である監査法人でポータブルPCが支給された時代に始まり、重さ8kg、容量4MBのデバイスを担いで利用したりしながら半年ごとにスペックが改良されていくのを見て、ハードウェアに興味を持ちました。さらに、Windows 3.1のリリース後、ソフトウェアに興味が移り、ウイルスに感染した経験を経て、ソフトウェアを作る一人ひとりの「心」が重要だと気づきました。一見ドライなITにこそ「心」が大切だと認識したことが、「テクノロジーに、ハートを込めて。」という言葉に結実したわけです。
守本:テクノロジーの裏にある思いという意味では、私の場合、証拠が存在しないために捜査や裁判の結果が変わってしまうという不平等の解消を目指し、デジタルフォレンジックの活用に取り組んだことがそれに当たるでしょうか。証拠データの効力は、最終的にはヒトが判断するのですが、それでもドキュメントレビューのプロセスを効率化し、技術的に再現することによって、不平等を少しでも解消できないかと思ったのがきっかけです。現在、開発を進めている診断支援AIシステムも同じで、専門医がいないために適切な診断を受けられない地域があるという現状に対し、それを技術でなんとかしたい、フェアネスを追求したいという思いを持って取り組んできました。

―― 売上高がこの10年で約2倍になったというのは目覚ましい成果です。
森:2011年の社長就任直後は、経理出身で“ぽっと出”の自分に対して、社内でも「あの人誰?」という反応が多数でした。社員の中には、日ごろ常駐先で働いている社員もいるため、フォーカスシステムズに対しての帰属意識が少ない社員も多く、その反応もある程度は致し方なかったと思いますが、社長としての自分の意志を伝えることは、当初は容易ではありませんでした。そこでトップとして社員をまとめるにはどうしたらよいかと考え、まずは二部上場、さらに一部上場を目指そうという方向づけを行いました。会社設立は1977年、1996年にJASDAQ上場、2016年に東京証券取引所市場第一部に上場と、それぞれ約20年の歳月がかかりました。面白いことに、チームを作り、システムを見直して売上利益計画を立てて頑張ろうと励ますと、社員は結構ついてきてくれました。年度初めに、数字をトップダウンで決めて「やれ」と号令をかけても、社員のやる気は上がりませんでした。そこで、ボトムアップで社員自ら数字を上げさせる方向に持っていきました。
社長就任後は投資家からは堅実な会社と評されていましたし、身近な人からは、経理マンらしいつまらない会社とも言われていました。しかし、売上も利益も上がっているが利益率が下がっている現実を直視し、今後の経営計画にどう改善案を盛り込むか考える必要に迫られたわけです。
守本:ボトムアップで数字をあげていった例のように、社員自らが売上の数字を積み上げた結果、利益率が追い付いていくといったイメージでしょうか。
森:「数字を達成すれば上場」という目標を掲げていたことと、アベノミクスの追い風も大きかったです。数字をクリアして上場しようという全社的な盛り上がりを作れました。
―― 官公庁と民間双方の顧客を相手とするビジネスの醍醐味は。
森:官公庁・民間の担当スタッフに求められるものは大きく異なるため、初期の段階で担当者を分ける方針としました。例えば、同じ部署に長くいる人の価値が高く、部長が一番なんでもよく知っているのが当然でした。対して民間は3カ月ごとにITトレンドが入れ替わり、他部署との横串や全社的なつながりが少ない世界です。現場の反対がありつつも、若い課長レベルのローテーションができるのが民間です。民間での売上の多くを占める、ある外資系の大手IT企業は、元々開発は東南アジア主体、インフラが日本主体であったため、開発はその企業内ではあまり行っておらず、自前では携わらない一定金額以下の仕事はプレミアムパートナーに完全に振るという大胆な仕組みを取っていたため、そこをチャンスだと思い、自ら行動しました。その後、大手IT企業・フォーカスシステムズ・その他の企業といった連合軍のチーム編成を1次請けとして提案できるまでになりました。
私はITについてはよくわからないので、日ごろどうせよという細かい指示は出していません。既存業務においては、現場に一定の裁量権を持たせています。新規事業分野も、新しく採用した人に任せる方針ではなく、事業創造室で手を挙げた社員に振っています。産学連携コンテストで委員をやっていて、フォーカスシステムズ賞を設定し、大学とコラボするなど面白い取り組みを進めています。その分野の一つが例えば医療です。

森:企業規模が大きくなると、必ず社会全体に対する責任が生じます。私は、会社は株主だけではなく、社員と社員の家族のものと考えています。そのため、会社の付加価値を作らないといけない。まずは個人が付加価値を発揮する。その後チームレベルでの価値を発揮する。その価値を社会に拡げる。オーケストラに例えてみましょう。いわゆる個人練習が個人責任。指揮者から合奏で指示されるのが企業責任。それを評価するのは聴衆、それが売上、社会責任です。自分たちなりに懸命に奏でても、聴衆が良いと評価してくれなければ良い音楽といえません。そのような中で、社員一人ひとりがどう価値を発揮するべきかについて、地道な努力ですが、説明や社長講和などを通じ、繰り返し会社の状況説明と併せてトップの言葉で語ることを心掛けています。
守本:社会課題は課題であるだけに、一筋縄では解決できません。AIテクノロジー、事業を通じて社会に貢献することはそんなに容易ではありません。FRONTEOでも、事業や地域の拡大において、リソース、タレントを補完しまとめることに日々努力と苦労の連続です。信念をもって事業を運営し続けることはなかなか難しく、事業が好調なタイミングで入社し曇り空が見えると辞めてしまうメンバーもいますが、業績が思わしくない時に一緒に乗り越えてくれるメンバーと並走しながら邁進しています。
森:今を支えてくれる当社の社員の多くが、右肩上がりの業績を当たり前と思っていることを危惧しています。悪い時期のフォーカスシステムズを知らない社員が増えました。このままいけるというぬるま湯感、新しいことをやらなくてもいけるという感覚にならないような働きかけを必要とする時期にきています。
―― AIを含めた新しいビジネスモデルへの展望についてお聞かせください。
森:プロジェクトの作業時間や日数に応じて必要な人数をあてがう人工商売に限界を感じ、一次請けや自社製品開発などを積極的に進めているところですが、新しい分野、ビジネスモデルの開拓は必然といえるでしょう。教育分野はとりわけ開拓の余地があると見ています。教育機関、特に大学は、少子化による学生数の減少を背景に、DXを進めないと淘汰されていくことは明らかです。しかし、大学はコンサバティブな世界なので、どうビジネスをねじ込むかは手腕が問われます。現在、医療分野におけるAI画像解析等の共同研究を産学連携で行っていますが、医療分野も伝統的に縦割りが多いですね。だからこそそういう分野で面白い展開ができればと考えています。
守本:医療分野においては、私も事業をさらに発展させたいと思っています。AIテクノロジーの勝ち組企業というのは実はないのが現状で、だからこそ日本を革新的なAIの発信地としたいと意気込んでいます。当社のビジネスは、AIによる弁護士、医師、経済安全保障などの専門家の判断支援ですが、ちょっとした気づきが真理の追究につながるので、これを極めていきたいですね。
同じカテゴリの記事
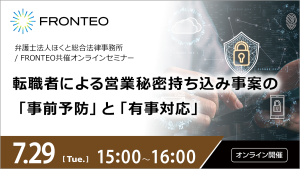
【7/29開催オンラインセミナー】転職者による営業秘密持ち込み事案の 「事前予防」と「有事対応」

【7/23開催オンラインセミナー】米国訴訟の基礎と実務~ディスカバリー対応を中心に考える日系企業の戦略的マネジメント~

【7/17開催オンラインセミナー】米国特許損害賠償を紐解く

【7/18開催_株式会社Re-grit Partners×株式会社FRONTEO共催セミナー】発生し続ける問題・不祥事に対応するために ―潜在リスクも見据えたフォワードルッキング型への転換―

【7/3開催オンラインセミナー】DX化時代の新たな脅威とそのリスクマネジメント

【6/30開催オンラインセミナー】データを国内に保存すべきか:ディスカバリの越境的適用とガバメントアクセスへの対応

【6/19開催オンラインセミナー】企業におけるセキュリティ・クリアランス制度の対応、活用及び応用

【6/26開催オンラインセミナー】既知から未知を発見するAI創薬支援サービス 「Drug Discovery AI Factory」

【6/25開催オンラインセミナー】“気づける法務”が企業を守る ~調査×通報促進・制御~ 実務担当者が今知っておくべき「早期火種対応」の実践知




