取締役

代表取締役社長/最高経営責任者 CEO
守本 正宏 Masahiro Morimoto1966年、大阪府生まれ。1989年防衛大学校卒業、海上自衛隊の護衛艦で勤務。退官後、半導体製造装置メーカーのアプライドマテリアルズジャパン株式会社を経て、2003年にUBIC(現FRONTEO)を設立。グローバル企業の国際訴訟対策をビッグデータ解析技術で支援し、また、自然言語処理と人工知能の研究成果を応用したAIエンジン「KIBIT(読み:キビット)」の開発・実用化を推進。2007年に東証マザーズ(現:東証グロース)上場、2013年に米国NASDAQ上場*を果たす(*2020年2月に上場廃止)。現在は、事業分野を創業事業であるフォレンジック調査、国際訴訟支援をはじめとするリーガルテックAIに加え、ライフサイエンスAI、ビジネスインテリジェンス、経済安全保障に拡大し、FRONTEOグループCEOとして事業展開ならびにAIの研究開発を牽引している。公認不正検査士(CFE)、NPO法人デジタル・フォレンジック研究会理事、警察政策学会会員。2025年4月 公益社団法人経済同友会 幹事就任。

取締役/CSO(Chief Science Officer)
豊柴 博義 Hiroyoshi Toyoshiba早稲田大学大学院 理工学研究科数学専攻。理学博士(数学、2000年に博士号取得)課程中の1999年より九州大学医学部附属病院の医療情報部にて医療データの統計解析を担当。2000年よりアメリカ国立環境健康科学研究所(NIEHS)において、データ解析による発がんプロセスの研究などに参加。2004年からは独立行政法人国立環境研究所にて、毒性データの統計解析・疫学研究のデザインとデータ解析の研究に従事。2006年に武田薬品工業に入社し、バイオインフォマティクス分野の研究員、グローバルデータサイエンス研究所・日本サイトバイオインフォマティクスヘッド、サイエンスフェローを歴任。また、臨床試験データにおける遺伝子発現データ解析やターゲット探索、さらに免疫と癌におけるバイオマーカー探索にも携わる。 2017年FRONTEOに入社し、ライフサイエンスの領域に特化したアルゴリズムを開発。テキストのベクトル化という特徴を生かし、現在までに論文探索、創薬支援、認知症診断支援、転倒予測などのさまざまなAIソリューションを開発。 2021年執行役員に就任。2024年より取締役に就任し、CSOとしてライフサイエンスAI事業の更なる成長を目指す。
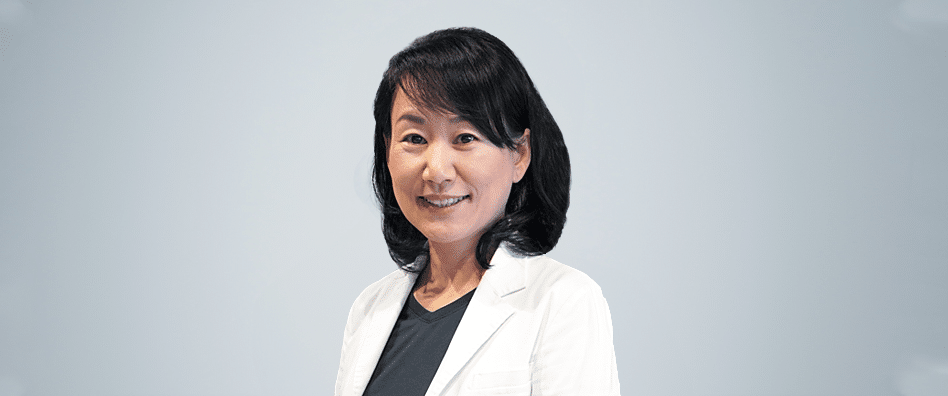
取締役
山本 麻理 Mari Yamamoto広告代理店に入社後、リスクマネジメント会社に在籍。メンタルヘルスケア事業を立ち上げ、事業計画、商品開発、マーケティング、営業戦略を実行し同社を業界トップシェアへと導く。2014年に取締役に就任し、2017年に東証一部上場を実現。 2018年に FRONTEOに参画、2020年取締役に就任。
社外取締役
取締役 舟橋 信 Makoto Funahashi |
取締役 桐澤 寛興 Hirooki Kirisawa |
取締役 永山 妙子 Taeko Nagayama |
取締役 鳥居 正男 Masao Torii |
社外監査役
常勤監査役 須藤 邦博 Kunihiro Sudo |
監査役 安本 隆晴 Takaharu Yasumoto |
監査役 大久保 圭 Kei Okubo |
執行役員

執行役員
池上 成朝 Naritomo Ikeue千葉大学理学部卒業後、半導体製造装置メーカーのアプライドマテリアルズジャパン株式会社に入社。 2003年に設立間もないUBIC(現FRONTEO)に入社。デジタルフォレンジックビジネス、ディスカバリ支援ビジネス(国際訴訟における証拠開示支援)、及びリスクコンサルティングビジネスなどの営業や企画を幅広く統括し、FRONTEOの創業事業である各ビジネスの立ち上げに大きく貢献した。2015年以降、新規事業立ち上げとして、自社開発の特化型AI「KIBIT(キビット)」の活用分野の拡大に取り組み、現在のビジネスインテリジェンス分野やライフサイエンス分野の礎を築く。
リスクマネジメント事業の新設に伴い、ビジネスインテリジェンス・コンプライアンス支援分野、リーガルテックAI分野、及び経済安全保障分野の事業統括として、これまでの実績と経験を活かし、「平時」・「有事」の両側面からクライアントのリスク解決に向けた包括的なソリューション導入、サービス提供に全力を注ぐ。

執行役員
渡邉 輝明 Teruaki Watanabe北里大学獣医畜産学部を卒業。新卒としてエンジニア系人材派遣サービス会社に入社した後に、ローコード開発を中心として幅広いDXを推進する株式会社パイプドビッツ(現スパイラル株式会社)に入社。その後、サイバーセキュリティ事業を展開する株式会社フーバーブレインでは、営業企画室長(執行役員)、NWセキュリティ事業部(取締役)を歴任。 2022年4月より株式会社アルネッツの取締役に就任し、2023年5月には代表取締役に昇格。経営全般を指揮し、営業・開発体制、間接部門の強化を行い、DX事業を二桁成長するビジネスへと牽引し、同社の持続的な成長に大きく貢献。
2025年4月、FRONTEOによるアルネッツ子会社化により、FRONTEOのビジネスインテリジェンス・プロフェッショナル支援とアルネッツのDX内製化支援、システム開発分野を統括するDX事業担当執行役員に就任し、今後も成長が期待されるDX市場において、FRONTEOのDX事業を次のステージへ押し上げていく。
現在、アルネッツの代表取締役も兼任。

執行役員
國枝 宏美 kunieda hiromi半導体関連商社に入社後、税理士事務所在籍。2012年にUBIC(現FRONTEO)に入社以来、経理財務を中心に従事してきた。海外のM&Aにおいては、投資先のPMIや内部統制構築において中心的な役割を果たすなど、その後日本だけでなく、米国、韓国子会社の経理財務を統括し、FRONTEOのグローバル展開に大きく貢献。
2021年より経理財務統括部長、2023年にFRONTEO Korea, Inc.の取締役に就任。
2024年にコーポレート担当執行役員に就任し、経理財務、人事、法務知財、総務、情報システムのコーポレート部門を幅広く管掌。経理財務の高い知識と専門性に加え、長年にわたる当社での経験を活かし、財務基盤の強化や基幹システムの導入による管理会計の強化のみならず、より積極的なIR活動を推進させ、FRONTEOの企業価値の更なる向上を目指す。
アドバイザリーボード

戦略アドバイザー
伊藤 俊幸 Toshiyuki Ito
防衛大学校機械工学科卒、筑波大学大学院修士課程(地域研究)修了。海上自衛隊で潜水艦乗りとなる。潜水艦はやしお艦長、在米国日本国大使館防衛駐在官、第2潜水隊司令、海上幕僚監部広報室長、同情報課長、防衛省情報本部情報官、海上幕僚監部指揮通信情報部長、海上自衛隊第2術科学校長、統合幕僚学校長、海上自衛隊呉地方総監を経て、2016年より金沢工業大学大学院(虎ノ門キャンパス) 教授を務める(イノベーションマネジメント研究科 イノベーションマネジメント専攻)。
専門:リーダーシップ・フォロワーシップ、リスクマネジメント、防衛・安全保障
論文・著書
・学位論文:ロシアの外交政策(文化人類学的側面からの分析)
・著書:『参謀の教科書』(双葉社 2023年)
・監修:『防衛シミュレーション! 自衛隊vs統一朝鮮』(宝島社 2020年)
・産経新聞正論欄・時事通信社コメントライナー執筆者、ニッポンジャーナル・文化放送「おはよう寺ちゃん」コメンテーター他、メディア出演
受賞:防衛駐在官勤務の功績に対し米国防長官より勲章「The Legion of Merit」、海幕部長勤務の功績に対し米国防長官より勲章「The Legion of Merit」を受賞
その他専門情報:全国防衛協会連合会常任理事を務める。

東京科学大学 総合研究院 特任教授
村田 昌之 Masayuki Murata1988年京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了博士(理学)。 1989年京都大学大学院理学研究科生物物理学教室量子生物学講座助手。その間、1993〜1995年ドイツ・ヨーロッパ分子生物学研究所(EMBL)、米国・カリフォルニア大学バークレー校に客員研究員として留学。1996年岡崎国立共同研究機構生理学研究所助教授。2003年東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻生命環境科学系教授。その間、東大・(株)ニコン社会連携講座「次世代イメージング画像解析学講座」特任教授兼任。東京工業大学科学技術創成研究院細胞制御工学研究センター特任教授兼任。2021年東京大学定年退職(東京大学名誉教授)。2021年より東京工業大学(現東京科学大学)科学技術創成研究院(現総合研究院)特任教授。2022年より東京工業大学(現東京科学大学)マルチモーダル細胞解析協働研究拠点拠点長(2022年10月~2025年3月)。東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(IRCN)特任教授兼任。自治医科大学客員教授兼任。
形態情報(細胞生物学や生物物理学など)と分子情報(生化学・分子生物学など)を結びつけた新しい生命科学の創設を目指し、大量の細胞(染色)画像を基に、細胞内のタンパク質を中心とした生体分子の時間的同調性を指標に細胞状態を層別化する「共変動ネットワーク解析技術(PLOM-CON法)」を開発。また、細胞膜を一時的に透過性にして、細胞内のオルガネラや細胞骨格の形態やそれらの立体配置を保持したままで細胞質を交換し、同調した細胞質環境で生起する多様な生命現象(シグナル伝達やオルガネラダイナミクスなど)を分析的に再構成できる「セミインタクト細胞リシール法」を構築し、さまざまな病態モデル細胞を作成してその病態発現因子を解析する手法を確立。前者は、特定の条件の細胞状態を作り出す「細胞設計」と「細胞評価」に利用できる技術で、後者は、細胞のジェネティックな改変なしに、細胞のドラマタイプを変えて「細胞編集」を可能にする新技術。これら二つの新しい技術を組み合わせ「細胞の設計→編集→評価→」を高速に循環させることにより、層別化された新薬の薬効、主作用・副作用、毒性発現のネットワークを用いた解析や、遺伝子改変を伴わない安全で新しい機能賦活化細胞作成を実行する「細胞デザイン」拠点創成に取り組んでいる。

弁護士(弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所)・公認不正検査士
早川 真崇 Masataka Hayakawa1999年東京大学法学部卒業。2000年検事任官(東京地方検察庁)。千葉地方検察庁(特別刑事部)、ワシントン大学ロースクール客員研究員、東京地方検察庁(特別捜査部)、法務省刑事局付(総務課)、徳島地方検察庁(三席検事)等を経て、2014年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)。2015年5月渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー、2016年1月同事務所シニアパートナーに就任し、危機管理プラクティスグループを統括。「かんぽ生命保険契約問題 特別調査委員会」委員を含む上場会社の第三者委員会委員を務めるとともに、その他の企業不祥事に係る調査案件、インサイダー取引・相場操縦等の金融商品取引法違反事案等における当局による調査・捜査対応、危機管理広報法務等の有事対応の助言のほか、平時のコンプライアンス・リスク管理体制の構築・強化、内部通報制度の構築・運用などに関する助言、AIを利活用したビジネス創出に関する法務などを幅広く手掛ける。
2022年4月日本郵政株式会社常務執行役・日本郵便株式会社常務執行役員、2023年6月日本郵政株式会社専務執行役・日本郵便株式会社専務執行役員に就任し、日本郵政グループのCCO(Chief Compliance Officer。コンプライアンス責任者)として、不祥事後の信頼回復、グループガバナンス・コンプライアンス・リスク管理体制強化に取り組む。内部通報制度・ハラスメント相談制度の改善、グループの企業行動基準の浸透、自然災害を含む危機管理体制強化、コンプライアンス・リスクを含むリスク管理の高度化、企業風土・カルチャー改革、AI等のテクノロジーやソリューション等を活用したガバナンス・リスク管理・コンプライアンス(GRC)領域の業務の標準化・効率化・高度化により、各種仕組みの構築と運用の改善・定着(PDCAサイクルの実践)に取り組んできた。退任後の2025年4月からは、企業の経営判断の高度化に向けた支援、ガバナンス・リスク管理・コンプライアンス・サステナビリティ領域におけるベストプラクティスを横展開し、企業の2線(法務・コンプライアンス・リスク管理・サステナビリティ推進等の管理部門)の機能強化に向けた支援に取り組んでいる。2025年4月FRONTEOの顧問に就任。弁護士(弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所)・公認不正検査士。
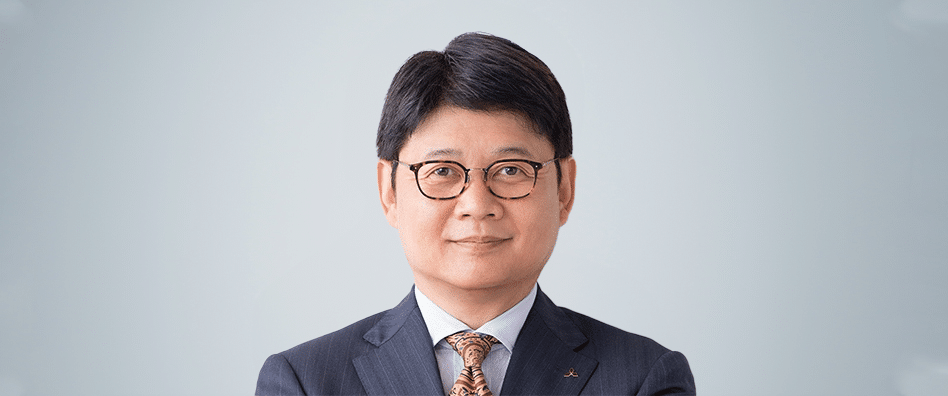
元三菱電機 執行役員 経済安全保障統括室長
伊藤 隆 Takashi Ito1986年、慶應義塾大学法学部法律学科卒業。同年、三菱電機株式会社入社。半導体のマーケティング、事業計画策定に携わる一方、業界再編や通商摩擦、国際カルテル訴訟解決を主導。1995~1997年、日本経済団体連合会(経団連)に派遣。欧州各国政府・財界と日本財界の連携強化に従事。
2020年10月、三菱電機が経済安全保障統括室を設置したのに伴い室長に就任。経済安全保障情報の分析とリスク制御に加え、企業における経済安全保障の重要性・具体的活動について積極的にアウトリーチを実施。2023年4月、執行役員に就任。2025年3月退任。2025年4月、FRONTEOの顧問に就任。
